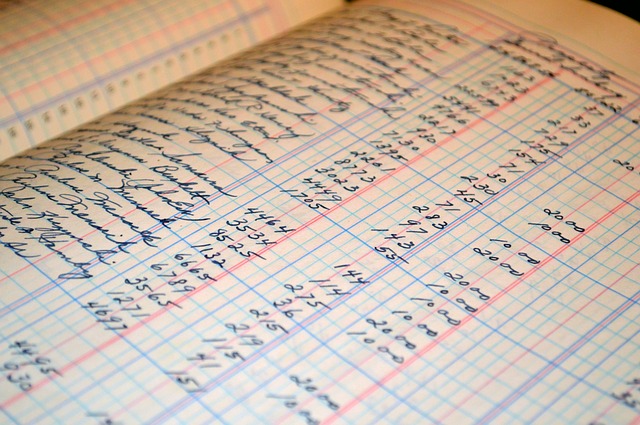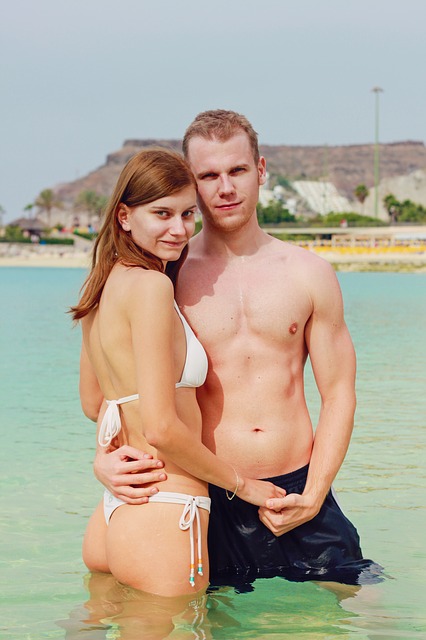みなさん、おはようございます。仙台税理士・公認会計士の伊藤宏平です。
前回、配偶者控除に代わる、夫婦控除が導入予定だというお話をしました。
今回は、夫婦控除の動向について簡単にお話しします。
目次
【現状の動向】
そもそも、夫婦控除とは、現状の配偶者控除(専業主婦世帯に有利な制度)を廃止して、配偶者の働き方に関係なく所得税額を軽くするものでした。
2017年度の税制改正として導入を予定していました。
しかし、今になって、税収減を抑えるため年収制限を導入すれば負担増が中所得者層にまで及び可能性が浮上しているようです。
【導入の問題点】
現行の配偶者控除の対象世帯数が1,500万世帯に対して夫婦控除の対象は、さらに拡大するため、控除額の対象者数が増えるイコール、税収が下がります。
税収減の対策として所得基準を設定して、基準を上回る世帯には適用されない仕組みを考えているようです。
当初の夫婦控除の対象外とする基準は800万円~1,000万円と例示しているようですが、さらに引き下げて500万円~600万円まで引き下げを想定しているようです。
この場合、中所得者層(500万円~600万円世帯)に対して負担が増加する可能性があるため反発が見込まれます。
【まとめ】
夫婦控除は、現代の配偶者の働き方に合わせて設計されています。
専業主婦(主夫)ではなく、勤務形態として共働きが増加している状況で
103万円までの収入であれば配偶者控除の適用がある。
一方で103万円を超える所得を稼いだ場合、配偶者控除(配偶者特別控除も含む)の適用も受けられない実態を改善する必要があります。
この所得税の改正は、従来の配偶者控除の適用世帯および不適用世帯にとっても大きな影響を与える改正であるため、政府には、ぎりぎりまでしっかりと議論してもらいたいと思います。
仙台税理士・公認会計士の伊藤宏平でした。
それでは、また。